
阿智神社から天竜川に沿って諏訪に向かって北上すると、駒ヶ根市赤穂に「大御食神社」(おおみけじんじゃ)が鎮座しています。

祭神は「日本武尊」(やまとたけるのみこと)。

境内に聳える御神木「御蔭杉」(日の御蔭杉、月の御蔭杉)は、ヤマトタケルがエミシ東征帰路の途中で当地を通過する際、大樹の元に仮宮を設けて当地の首長であった赤須彦のもてなしを受けたという場所であり、「尊大いに悦ばれ この杉の樹蔭清々しく弥栄えて丈高く奇杉なりと愛で給ひぬ以後この杉を御蔭杉と称せし」と社宝『神代文字社伝記』に記述されているそうです。

杉の根元には石が突き出ており、ヤマトタケルが手を掛けた「御手掛石」と伝承されます。

これは今流行りの要石に似ていますね。

御蔭杉はまことにもって立派な御神木ですが、204年(神功皇后4)年春に枯れて、翌年春に中枝の大虚に実生の杉の植継を行ったとされ、さらに856年(斉衡3年)年5月に枯れて、858年(天安2年)年春に再び植継を行って現在に至ると伝えられているそうです。



さて、あらためて拝殿を参拝しますが、祭神はヤマトタケルの他に、后神の宮簀媛を「五郎姫神」(いついらつひめのみこと)、他に八幡大神として「誉田別尊」を祀ります。

五郎姫神は応神天皇8年に尾張国より勧請したとされ、鎮守の杜「美女ヶ森」の名の由来となっています。

誉田別尊は元慶3年(879年)に石清水八幡宮より勧請されたそうです。

回廊状になった拝殿の奥の左手に檜造りの建物があります。
これは「神饌殿」であり、神前に供える「御饌」(みけ)を調理し格納する建物で、これが社名の由来かと思いきや、もともと天皇の「御真影」と「教育勅語」を納めていた赤穂小学校の建物を、昭和22年(1947年)に移築したものだそうです。

では社名の大御食神社の由来はどこにあるのか、それはもう穀物神「御食津神」(みけつのかみ)にあるとしか思えないのです。

当社の宮司を代々務めるのは阿智祝部の支族・赤須氏です。
阿智神社が破損した際には、改築のため大御食社大足葦津彦が派遣されたという記録もあり、阿智神社との古い繋がりが示唆されます。

御食津神とは、「大宜都比売」(おおげつひめ)・「保食神」(うけもちのかみ)・「宇迦御魂」(うかのみたま)・「豊受大神」(とようけのおおかみ)・「若宇迦乃売神」(わかうかのめのかみ)など、穀物神の総称であり、ケツは狐の古語であることから、稲荷神の「宇迦御魂」(うかのみたま)の異称ともされます。

ヤマトタケル(ハリマタケル)が当地に立ち寄ったかどうかは分かりませんが(ハリマタケルは東征先の香取神宮の地で亡くなったと考えられます)、当社の本来の祭神は御食津神であったと思われます。越智族が阿波にオオゲツヒメを祀ったように、阿智氏が信濃に穀物神を祀ったのでしょう。

大御食神社境内に佇んでいると、影の古代氏族が祀り続けた、大いなる神の息吹を感じるものです。

尚、大御食神社には神代文字で記された『神代文字社伝記』が存在しているそうですが、僕は神代文字については今のところ否定的立場です。



大御食神社からほど近い場所に「大宮五十鈴神社」(おおみやいすずじんじゃ)があります。

応神天皇39年、尾張国熱田神宮より熱田大神の御分霊を迎えて奉斎したのが起源だと伝えられます。

奉斎したのは大御食神社の創始者である御食津彦の子、瑞武彦と云うことです。

境内の池には、なぜかツチノコを抱えたカッパがいました。。

応神天皇42年に伊勢国の神宮より天照皇大神、諏訪大社より建御名方命を迎え相殿に祀り、伊鈴神社と称したといいます。

当地は江戸時代は三州街道の上穂(うわぶ)宿で、賑わっていたようです。
今も例祭で行われる丸太を刳り貫いた巨大な大筒による豪快な三国花火が有名。
降り注ぐ火の粉の中に、上半身裸の男衆が競うように飛び込んで行くのだそうです。

それにしても何故に熱田大神を奉斎したのか。大御食神社がヤマトタケル設定だからでしょうか。
しかし時代は応神帝・竹葉瀬ノ君の頃なので、物部系であるヤマトタケルに忖度する必要はないと思われます。
大宮で五十鈴神社っていうんだから、主祭神は元々アマテラスの方だったのではないでしょうか。

信濃は仁科家なども来ていますから、どうにもやんごとなき事情があったのかもしれません。

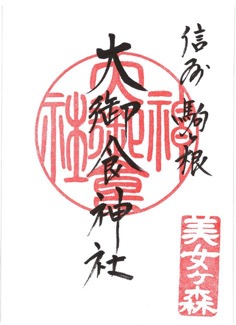
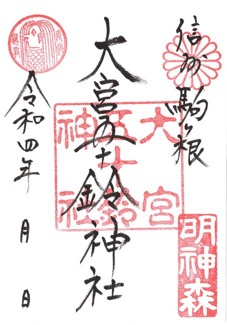
narisawa110
この神社、いつの間にかオモイカネが居なくなってしまったのですかね。
そういえばと思い直して見たんですが、ナイ。
あと、本地垂迹説で行くと、オモイカネは虚空蔵菩薩なんですね。
山形の蔵王の西側には慈覚太子が開いた龍山がありますが、麓の蔵王成沢地区には近くに単独で虚空蔵菩薩を祀る神社があります
成沢八幡宮の里宮裏手には合祀された幸神もちんこいのがあります。
蔵王信仰と虚空蔵菩薩(オモイカネ)は近いのだとすれば、やっぱり物部と阿智のエリアなのですかねー
いいねいいね: 1人
昔はオモイカネも祀られていたんですか?
蔵王とオモイカネ、そんな組み合わせもあるんですね。
いいねいいね
この神社、私も行きました。
応神期にはすでに諏訪大社の祭神がミナカタになっていたのかもしれない貴重な伝承があるんですね
長野県には熱田社が結構ありまして、長野県朝日村、伊那市高遠(長谷だったか?)などに点在します
オオミケを大御神と解釈するのか、オオミケを太田氏の大王の名に当てはめるのか、悩ましいところですね
長野県のタケル伝承は碓氷峠から中央道あたりまでの広範囲に広がりますので物部士の信濃入りの時期に関しては謎が多いですよね
あと、富家伝承に全く出て来ない神様のことも気になります
オモイカネや瀬織津姫ですね
瀬織津姫はなんとなくのイメージなのですが中臣家が後年に広げようとした神様の様な気がしています
故に比較的新しい神社にも祀られているんじゃないかと
いいねいいね: 1人
大宜津比売と保食神の神話と大御食神、これの意味するところが気になっています。前2者はそれぞれスサノオもしくはツキヨミに斬られることで国土に豊穣をもたらします。
彼女ら穀物神とはいったい誰だったのか、それが少し、分かりかけて来たところです。
信濃国と熱田社の関係も気になりますね。
はやく長野にも行きたいのですが、その前に行かなければならないところも多く残っています。
瀬織津姫は常世織姫のことだと確信していますが、多くの時代で象徴のように扱われて来たので、なかなか探るのが難しいですね。
いいねいいね