
「お久しぶりです。
遅くにすみません。」
そう言って、彼がメッセージをくれたのは、2年前のことでした。

彼は昭和初期に編集された「村史」を読んでいて、思いがけない発見をし、嬉しそうに僕に報告してくれたのです。

彼が教えてくれた場所を訪ねに行くと、近くに「菅原天満宮」なるものがありましたので、まずは遠地に祀られた氏神様にご挨拶することにしました。

縁というものは不思議なものです。
こんなおっさんにも、古代史大好きな出雲の高校生(当時)と、一つの話題でつながることができるのですから。

あの先にあるのは何だろう。

荒神様か何かが、あったのでしょうか。



さて、場所はだいたいこの辺りのはずですが、入口は、どこだ?

あった、あった。入口を探すだけで、すでに汗まみれ。

彼が興奮して教えてくれたのが、島根県出雲市船津町、斐伊川沿いに鎮座する「船津神社」(ふなつじんじゃ)でした。
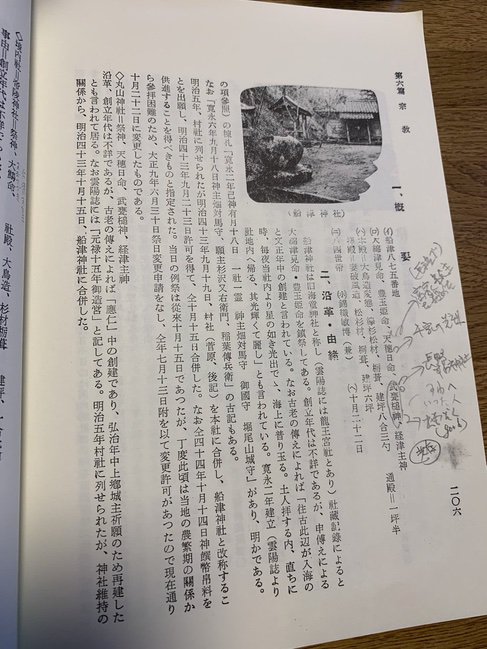
彼が調べたところによると、船津神社の名称は明治時代に改称されたもので、元は「海童神社」を称していたとのこと。
さらに、江戸初期の旧海童神社の神主の姓は「畑」(はた)で、この方は徐福と共に出雲にやってきて定住した海童の子孫ではないかと推察しています。
残念ながら畑さんはその後移住されたらしく、現在町内に畑さんはいらっしゃらないということまで、調べていました。

うぬぬ、やはり登らされますか。

現在、出雲で海童神社を名乗るのは、出雲市島村の斐伊川河口に鎮座する神社があり、斐伊川を挟んだすぐ隣にはかつては中洲だったことを示す「浮洲神社」が鎮座しています。
また、浮洲神社から少し先の浜ノ場にも海童神社が伝わっていました。

つまり、出雲にも、この船津神社を含め、斐伊川沿いに3社の「海童神社」があったことを示しています。

滝の様な汗で禊を終えた僕は、ようやく船津神社に到達しました。

低山山頂に祀られる神社。

村史には、
「古老の伝えによれば、往古此辺が入海の時、毎夜当社内より星の如き光出でて、海上に普り玉る。土人拝するうち、直ちに社地内に帰る。その光輝くて、麗し。」
とあり、少年は「これはユダヤの血を引く秦族(海童たち)の星への信仰があったことを示しているのではないかと思いました」と感想を述べています。
ブラボー!

船津神社の祭神は、主神に「大綿津見命」を祀り、「豊玉姫命」を配祀しています。
他、「天穂日命」「武甕槌命」「経津主命」を合祀。

彼の話では、
「昔はその近くに中洲があったらしく、海童たちが蓬莱山信仰のもと、その辺りを聖地と考え、船津神社を建立したと思います。船津神社は山の頂上にあるので、そこから星を拝んでいたのではないでしょうか」
ということです。

いやまったく、その情景が目に浮かぶようですね。
素晴らしい。

僕は今、日本最大の中洲にかつてあった、とある神社の探求に心奪われています。
中洲、または川中島と呼ばれるそれは、古代から聖地として重要視されていたことを窺わせます。

船津神社は「頭痛」の神としても信仰されていたそうで、「ゴ石」「ナダ石」のなめらかなる石で頭や体をなで、ご利益を受けるのだそうですが、この本殿裏の石がそうでしょうか。

船津神社社殿の前に、目立つ境内社が鎮座しています。

その名は「帝神社」。
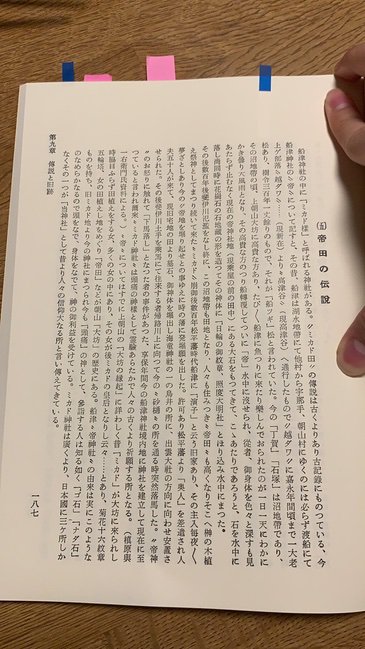
少年が教えてくれた村史によると、祭神は「大鷦命」(おおさざきのみこと)とあり、いわゆる仁徳帝を指すということになります。
「昔、朝山大坊(船津から山の方にある古寺)に、帝がいらっしゃって、田植えをしていた女のうち、1人を見初めて皇后とした。その後、船津がまだ沼地だったので、釣りをしていたところ釣り船が転覆してお亡くなりになった。地蔵に”日輪の御紋章、照度大明神”と彫り、転覆したあたりに投げ入れた。
後に船津が田地となってからは、そこは”帝田”と呼ばれるようになった。
帝田には榊を植え、その後もお祭りしていた。
その後、松江藩の治世に、船津の旧家の者が、帝田を掘り起こすべしという夢を見て、松江藩に願い出て、50人の人夫が派遣され、掘り起こすと例の地蔵がでてきた。それを御身体として祀った」とのこと。

う~ん、この伝承が伝えんとする意味がよくわかりません。
オオサザキ帝はまた闇を抱えたお人ですが。
また、船津神社は海童社として「特異な神」として地元民に信仰されてきたとのことで、「片目の視力のない神様」とも伝えられており、製鉄神「天目一箇」を彷彿とさせます。

少年はこれらを調べた上で、
「船津神社の祭神を見ると、海童たちが拝むであろう神と共に、武甕槌命も祭られています。船津神社の近くには竪穴住居の遺跡があり、海童たちが来る前に出雲族が住んでいたのは明らかです。よって、新らたにやってきた渡来系の秦族と地元の出雲族が仲良く同じ神社でそれぞれの神を祭り、共存していたのだと思います。
なぜ豊玉姫命が祭られているのかはよく分からないですが。九州の海童神社でも豊玉姫が祀られていたりするんでしょうか?
また、船津神社から2、3キロ離れた神社では大神神社から勧請した大物主命を祭っていて、ごりごりの出雲系なのに、近くの船津神社では秦族の神を祭っていて、同じ地域でうまく共存していたことがわかります。」
と、民族共存の様子に夢を膨らませていました。
そう、僕が思うに、出雲族が僕ら子孫に残してくれた最大の恩恵は、民族共存という幸せの道だったのではないでしょうか。
今は少年から青年へ、「古代史大好き出雲の高校生」から「古代史大好き理系の大学生」となった彼に、約束の地をようやく訪れた僕から希望を込めて、心から敬意を贈るのでした。

神社で繋がる縁、素敵ですね☆☆☆(ワタツミに因んで星3つ)
子孫繁栄も、古代史探求もこうやってご先祖から引き継がれていくんですよね^^
いいねいいね: 1人
素敵な御縁です😌
いいねいいね: 1人
古代史大好き大学生です。
まさか2年前のメッセージを元に訪れてくださるとは、感激です。
今も時々記事を拝見しています。
まだ当分猛暑が続きますので、お体にお気をつけ下さい!
いいねいいね: 1人
やあ、こんにちは♪たのしく学生生活をお送りでしょうか。
あれから船津神社に参拝するのに、2年もかかっちゃいましたw
日本はやはり、素晴らしさに溢れていますね。
お互い元気で、過ごしましょう!
いいねいいね: 1人