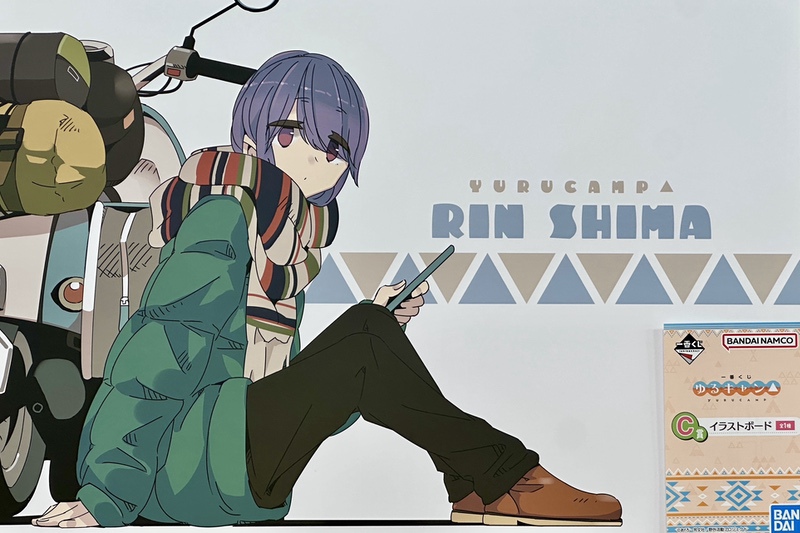
ところでリン、時間を稼ぐのはいいが
別に、アレを倒してしまっても構わんのだろう?

ということで、徳島県美馬郡つるぎ町、御所平に鎮座の忌部奥社「御所神社」(ごしょじんじゃ)に再びやって来ました。
「天日鷲神」(あめのひわしのかみ)を祭神とし、忌部神社の大元であると主張する神社です。

社碑によると、天日鷲命を奉祭する忌部族、即ち徳島県民の祖神を祭り、古来阿波の国の総鎮守の神社として、平安時代の延喜式内社に官幣大社と列せられた忌部神社こそ当社であり、四国随一の格式の大社として四国一ノ宮と称せられたとしています。
忌部神社は、中世以降の兵火、あるいは弾圧による社領の没収、御供料の廃絶により神社の呼称の改名することとなり、久しく社地の所在が不明となったため、社地が論争されてきました。

明治政府発足後、祭政一致の制により神社を国家の宗祀とするため、明治4年(1871年)、忌部神社を国幣中社に列することになりました。
これに各地から社地の名乗り出があり、忌部本宮を巡り、魔術師(マスター)とそのサーヴァントによる『聖杯戦争』(社地争い)が始まることになります。

その最終決戦では、御所平の当社と麻植郡山崎村の山崎忌部神社が争うわけですが、決着がつかず、全く関係のない徳島市二軒屋町に新たに忌部神社を設けることとなりました。
現在、御所神社は、徳島市の忌部神社の摂社となっています。

しかしまあ実際、御所神社を訪ねてみると、高台からの景色こそ素晴らしいものの、境内もさほど広くなく、実に簡素な神社で、元宮とか、奥社という雰囲気は、残念ながらあまり感じられません。というのが、前回参拝の僕の感想でした。
忌部一族の古代磐座祭祀場だったという話でしたが、これは見当違いかと、僕は早々に山を降りてしまったのです。

が、後で調べてみると、どうやら今の御所神社は200mほど遷座されたもののようで、その先の山中に旧跡地があるのだということです。
しかもそこには、立岩の磐座があるとの情報。
な・ん・で・す・と。

そんなわけで、少ない情報を頼りに、2023年12月、僕は御所平の山中を彷徨っているのです。
とりあえず尾根沿いの、このゲートのようなところに出て来ましたが、この先は崖のような急斜面なので、このゲートの上に登ってみます。

この辺から登れるのか、な?

なんとか歩けそうです。

道があるといえばあるような、無いといえば無いようなところを突き進みます。

四国に熊はいなかったよね、たぶん。

数分ほど歩いたでしょうか。気分的にはもっと歩いた気がします。

岩が乗った古墳のような丸い盛り上がり。

おおー、滑り落ちそう。。

よろけつつも何とか歩み進めると、尾根に沿って、岩の塊がありました。まるで地を這うヘビのようです。

コイツは頭か、尻尾か。

その先にも、でっかい岩の塊があります。

近づいて見ると、異様な圧に背筋がゾワリとします。

うおー、何だこれ。

尾根に沿って岩が積み上げられている。

こ、これは、あのUSA山の龍の磐座の原型ではないでしょうか。

長い体を横たえる龍神。

USA山の磐座よりも原始的に見えますが、しかしさらに驚くものが、その先に

ありました。

気高く鎌首を持ち上げた、獣の王。
間違いなくこれが、この聖地の主、蛇頭の磐座です。

身長180cmの僕の、ちょうど顔の位置くらいに置かれた小さな祠。
これが御所神社の元宮でしょう。
中には平べったい石が祀られています。

そして明らかに、人為的に積み上げられた頭部の磐座。
このような積み方の磐座を、僕はこれまでもいくつか目にしていますが、ここまで突き出たものは珍しいかもしれません。
くるま座のN氏は、この手の磐座を「亀の磐座」と呼んでおられましたが、この清頭岡磐座(きよずがおかのいわくら)は蛇体であるのは明らかです。しかも、

これはコブラではないでしょうか。僕はこれを見た瞬間、そう感じてしまいました。
もしそうなら、「阿波族の起源はドラヴィダ先発隊」説の有力な根拠となりうるのですが、今のところ断定はできません。

蛇頭の磐座は、先ほど見てきた尾根沿いの磐座群の頭部に当たるのだろうかと思いましたが、

こっちはこっちで、別に尻尾がありました。
つまり、尾根の磐座と蛇頭の磐座は、別の個体として祀られていた、ということになるのでしょうか。

尻尾はガラガラヘビにも見えますね。

角度によっては、スフィンクスか亀のような前足も見えます。

これは階段かな。

頭部を横から見た図。これはどうやって安定させているのだろうか。いつ落っこちてきてもおかしくないように見えますが。

古代阿波族は、採石能力に長けていたと思われますが、このような巨大な石積みもお手の物だったというのでしょうか。
巨大な生物を思わせる巨石を積み上げた磐座は、四国と瀬戸内沿岸部、九州、それに伊勢で確認できます。そしてそれらのほぼ全てが、山中深くひっそりと祀られているのです。
このことは、ピラミッド、ストーンヘンジ、モアイなど、世界中の巨石文明がその栄華と権力を誇示するように、平地にこれ見よがしに存在するのと対照的です。

日本における古代神(自然神)は、見ることはできない、見てはならない存在であったといいます。
この隠された磐座群は、そうした古代日本人の神の概念を表しているようにも思え、これらを創造した古代氏族もまた、表の歴史からは見えない存在としてあらんとする痕跡が、感じられるのでした。

💚
いいねいいね
narisawa110
気安く遠坂に近づくなと言われてるようなナイヨウナ?w
いいねいいね: 1人
遠坂にせよ志摩にせよ、女神とは近くとも遠い存在ですな。
いいねいいね