
宗像市神湊(こうのみなと)の丘の上に「宗像神社頓宮」があります。
ここは宗像大社の秋の例大祭で行われる「みあれ祭り」で、約200隻の船団にて行われる海上渡御の地で、御神体の御旅所でした。
なぜ御神体はここに立ち寄るのかというと、地元古老は、当地が宗像大社辺津宮の元宮だからと言い伝えているのだそうです。

当地は古くは「綱掛神社」と称していました。
今、この綱掛神社は麓に「津加計志神社」として遷されています。



「津加計志神社」(つかけしじんじゃ)に来ました。

まずはいつもの、階段の洗礼。

体から吹き出す水が、お清めがわりです。

漁村にある、素朴な神社。

津加計志神社の祭神は「市杵島姫命」、相殿に「吾田片隅命」を併せ祀ると古伝に記されているそうですが、他に宗像三女神であるなどの説もあります。
しかしながら、当社の真の祭神はやはり、宗像族初代王「阿田賀田須」(アタカタス)で間違いありません。

変わった社名の「津加計志」(つかけし)とは、「綱掛」(つかけし)のことであるとのことですが、どういった意味が含まれているのでしょうか。
津加計志神社の元宮は岬の上にありましたから、神の乗った船を岸につけるため、綱を掛けた聖地だったということになるのでしょう。

まさに海人族らしい、信仰の名残ある名跡です。



福津市生家の「大都加神社」(おおつかじんじゃ)に来ました。
大都加とは「大塚」のことであり、古墳の上に鎮座する神社です。

「筑前國續風土記付録」には、「いかなる神を祭れるにや」、つまり祭神未詳とあるようで、奉祀は修験者が行っていたとあるそうです。

祭神は現在、「埴安神」「少彦名命」「保食神」となっているそうですが、拝殿にかかげる祭神は、「大国主命」「田心姫命」「阿田賀多命」「宗像君阿鳥主命」他となっています。

宗像神といえば、宗像三女神との認識が一般的ですが、アタカタスの娘のうち、長女・田心姫は7代目出雲王「天之冬衣」(あめのふゆきぬ)に、次女・多岐津姫は8代目出雲王「八千矛・大国主」に嫁いでおり、二人とも出雲の地で生涯をおえておられます。
つまり、本来の宗像主祭神は「アタカタス」であると考えるのが普通だと思われます。

もちろん、姫神の御魂は故郷に還され、今は三女神が主祭神であることに異議はありません。
それにしても、アタカタスの存在感の薄さは、不思議としか言いようがないのです。

拝殿に掲げられた祭神の意味は、この宗像で失われつつある古来の由緒を、受け継ぎ伝える人がいるのだということかもしれません。



福岡市博多区上川端町、博多の氏神・総鎮守「櫛田神社」(くしだじんじゃ)にやって来ました。
地元の博多の人に「お櫛田さん」と呼ばれ親しまれる神社です。

7月の博多祇園山笠や10月の博多おくんちなどの祭事の中心となる神社で、5月の博多松囃子(博多どんたく)でも、松囃子一行がここから出発します。

祭神は「大幡大神」(櫛田大神)の他、「天照皇大神」、「素盞嗚大神」(祇園大神)の三神です。
全国の櫛田社が「櫛名田姫」を主祭神とするのに対し、当社では櫛名田姫は祀られていません。
大幡大神(大幡主命)は別名を大若子命といい、伊勢国松坂の「櫛田神社」から勧請した神とされています。

この大幡主は謎大き神の一柱ですが、九州王朝説を唱える方々は、この神を重要視されます。
個人的には大幡主の幡は、秦族のハタ、または豊族ゆかりの八幡宮のハタに関連があるように思われます。

社伝では、天平宝字元年(757年)に、松阪にあった櫛田神社を勧請したのに始まるとされ、松坂の櫛田神社の祭神の大幡主神が天照大神に仕える一族の神であったことから、天照大神も一緒に勧請されたと伝えていますが、平安時代末期、平清盛が所領の肥前国神埼(佐賀県神埼市)の「櫛田宮」を、日宋貿易の拠点とした博多に勧請したという説が最有力であり、昭和40年(1965年)に櫛田神社の宮司らが編纂した『博多山笠記録』や昭和54年(1979年)に福岡市が発行した『福岡の歴史』でも佐賀県神埼市にある櫛田宮の分社だとされています。
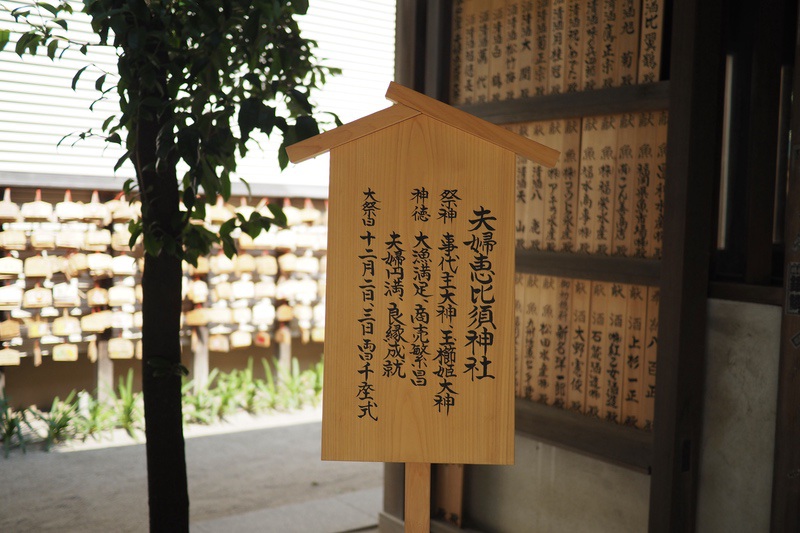
当社の一柱である素盞嗚大神ですが、天慶4年(941年)、小野好古が藤原純友の乱を鎮めるために京都の八坂神社に祈願し、平定した後に当社に素盞嗚神を勧請したと伝えられるのですが、拝殿内の扁額を見ると、「須賀大神」となっています。
一般に須賀大神はスサノオとの認識ですが、須賀(須我)の場合は、スサノオ=徐福ではなく、スサノオ=スガノヤツミミと考えた方が良いのかもしれません。

実際に櫛田神社境内社を見てみると、出雲系のものが多くを占めており、当地が出雲族の重要聖地出会ったことを偲ばせています。

肥前国神埼の「櫛田宮」の祭神は「素戔嗚尊」「櫛名田比売命」「日本武命」となっており、景行帝の伝承もあることから、物部色の強い神社となっています。
しかし、ヤマタノオロチ伝承も伝わっていることから、出雲族も当地にいたのではないかと推察できます。

【神埼櫛田宮 拝殿】
神埼櫛田宮の伝承では、元寇の時、櫛田宮の神剣が博多の櫛田神社に贈られ、合戦の時には数千万のヘビが海上に浮かび、戦いを勝利に導いたと伝えられます。
神紋にも「剣の交差紋」が使われており、出雲王家の関わりをそこはかとなく感じさせます。

同時にもう一つ、僕の頭をよぎるのは、四国にも剣交差紋があり、白蛇を信仰する一族がいたと考えられること。

この博多の櫛田神社境内社にも、そんな痕跡を感じなくもないのです。

さて、今回のお目当ての場所に向かいます。
その前に、古来から伝わる、秘密の禊を行います。
山笠小僧の御聖水を顔面に浴びます。
うそです。よい子はマネしてはいけません。

さて、境内社の石堂神社ですが、ここにアタカタスが祀られています。
この神社だけ、特別に石碑があり、由緒が書かれています。

なぜアタカタスが石堂なのか?
石堂大権現といえば徳島にその名の神社があり、一帯は剣山を中心とした修験道場となっています。
美馬郡つるぎ町半田日浦の尾根上にある石堂神社は、そばに高千穂神社があり、眼下には伊射奈美神社を祀る中鳥島を見ることができるのだそうです。
そこでは「月見」が有名で、昔から8月26日の深夜すぎに昇る月を見るのが恒例となっていたと伝えらえていました。
