
福岡市柏原に鎮座の「羽黒神社」(はぐろじんじゃ)を参拝します。

参道入口には、巨大な楠が四肢を伸ばしています。

当社創建は不詳。
『筑前国 続風土記拾遺』に天正14年(1586年) の当社に関する文書の存在を示す記録があり、江戸時代には福岡藩主の深い信仰を受けていたことを物語ります。

参道の階段を登ります。

すると階段の途中に、下からは見えなかった何かがありました。

「神殿跡」。なんだこれは?

辺りには謎の石垣があり、

手水もあります。
本当にここに、神殿があったのでしょうか。

神殿跡地というと、久山の伊野天照皇大神宮が思い出されますが、そこは本殿の裏手、境内の最も高い位置に木柱が立てられていました。

ここは参道の中程です。

何の神殿が、どんな神殿が建てられていたのかは情報がありませんが、確かに深い神氣を感じるのは間違いありません。

階段を登り終えると、比較的新しい社殿が見えてきました。

昭和20年6月、福岡空襲によって社殿は焼失しましたが,昭和21年氏子らによって再建され、現在の社殿は昭和55年に再建されたものとなっているとのこと。

かつての神殿は、荘厳な桃山造で文化財に相当するものであったということです。

当社祭神は「大巳貴命」(おおなむちのみこと)。社の案内で大国主と注釈が添えられていました。

当社は中世のころ、出羽羽黒山の修験者によって勧請されたと考えられています。
社名を見るに、確かにそうかもしれませんが、それでは祭神が少し妙だと思います。

確かに出羽三山には大己貴も祀られていますが、それは大山祗・少名彦とともに湯殿山に祀られているのであって、しかも湯殿山は後年、出羽三山に加えられたと聞いています。
三山最高峰の月山には月読命が祀られており、当社勧請元と思われる羽黒山・出羽神社には、出羽国の国魂である「伊氏波神」(いではのかみ)と「稲倉魂命」(うかのみたのみこと)の二神が祀られているのです。
神紋も当社は「亀甲に大」、羽黒山出羽神社はの祭神は「巴」となっています。

出羽三山の開祖は、32代崇峻帝の第三皇子「蜂子皇子」(はちのこのおうじ)であるとされます。
崇峻5年(592年)の冬、父である崇峻帝が蘇我馬子によって暗殺され、聖徳太子の勧めで宮を逃れ、当地に至り開山したというものです。
伝承では、蜂子皇子は越路(北陸道)を下り、能登半島から船で海上を渡り、佐渡を経て由良の浦に辿り着いた時、容姿端正な美童八人に会います。
不思議に思った皇子が近づくと、乙女らは皆逃れ隠れてしまい、そこに髭の翁があらわれ告げました。
「この地は伯禽島姫の宮殿であり、この国の大神の海幸の浜である。ここから東の方に大神の鎮座する山がある。早々に尋ねるがよい」
皇子はその教えに従い東の方に向かって進みましたが、途中道を失ってしまいます。その時、片羽八尺(2m40cm)もある3本足の大烏が飛んできて、皇子を羽黒山の阿久岳へと導きました。
これにより、由良の浜を八乙女の浦と称し、皇子を導いた烏にちなんで山を羽黒山と名付けた、ということです。

蜂子皇子は異形の姿で描かれることが多く、また何故か、伝承では八咫烏と思われる人物が突然登場し、皇子を導きます。

そして本来の羽黒神「伯禽島姫」(しなとりしまひめ)は、八乙女の浦の洞窟を母胎として誕生したとされ、この洞窟は羽黒山頂の霊地「鏡池」とつながっていると云われています。
この伯禽島姫は、龍宮の乙女「玉依姫」(たまよりひめ)であると当地では云われており、八乙女とは、八人の乙女ではなく「由良比売」(ゆらひめ)または「妙理姫」(きくりひめ)の化身だという説もあります。

出羽三山の最高峰を月山と名づけ、月読神を祀り、月読みの巫女である玉依姫=ククリ姫、すなわち越智家の常世織姫を羽黒神として祀っている姿が、出羽信仰からは読み解けます。
この福岡の羽黒神社のすぐそばには油山があり、そこの夫婦岩は、太宰府の夫婦の霊峰、宝満山と大根地山(越智山)を遥拝していました。
つまり、羽黒神社の真の祭神・羽黒神とは、月読みの巫女・常世織姫ではなかろうか、と僕は思うのです。
月にあり、龍宮を満たすという霊水は、「変若水」と書いて「オチみず」と呼びます。
夫婦円満で健康長寿、そんな信仰が、当社からは滲み出ていました。

本殿左側には「天神社」。
神社の案内では祭神は道真公となっていますが、福岡縣神社誌では埴安神となっている様子。

右側の「綾部神社」は祭神がわかりませんが、綾部(柿本)人麿なのか、な。



追記:X友のmonoさんから、次のようなコメントをいただきました。
“画像の氏子寿命鏡に埴安姫神社の名が併記されており、「神殿跡」が埴安姫神社跡だとしたら羽黒山三の坂の埴安姫神社の配置みたい꒰ ♡´∀`♡ ꒱”
なるほど!境内社の「天神社」祭神が、福岡縣神社誌では埴安神となっているのでそのことだろうと思っていましたが、敢えて社名を併記しているのは、羽黒神社本社と同格の社が境内に鎮座していたと考えるのが正しいですね。
同格の社というなら、境内社の天神社よりも、あの参道途上に広く敷地を設けられた、神殿跡にあった社の方であった可能性が高いように思われます。
おそらく出羽三山信仰を広めたのは、豊系のサンカであると思われ、当社も彼らが地元に近い当地に勧請したと考えられますが、しかしそれならば、羽黒神に関わる埴安神とは一体誰なのか、そんな謎が再び生まれ、沼にハマっていくのでした。
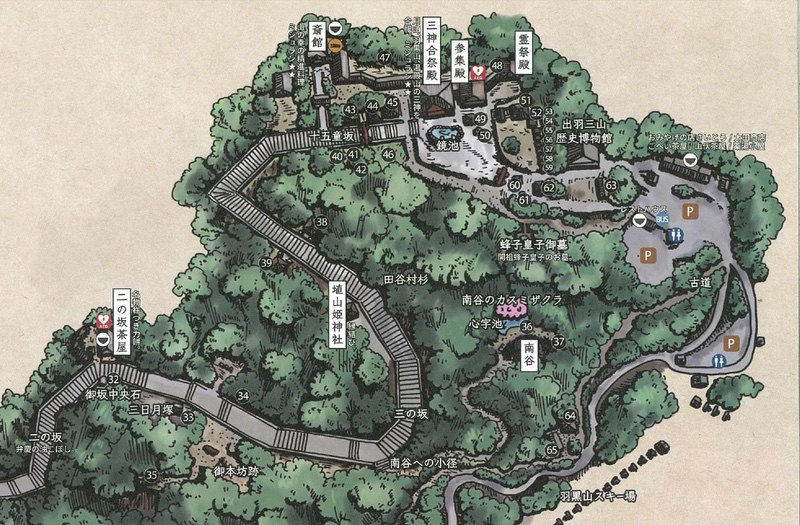
いいえ、奥の三つ鳥居ではなく、入り口のシンプルな形の鳥居が有るんですよ〜
いいねいいね: 1人
おお、そうなんですね〜・:*+.\(( °ω° ))/.:+
いいねいいね
narisawa110
鳥居の形が檜原神社に似てなくもない
いいねいいね: 1人
三つ鳥居の真ん中に似ている、ということですか?
僕にはありきたりの鳥居に見えますが。。
いいねいいね